�Ǝ����āA�l�\����̈Ӗ����炢���A���₩�ɐ�������͕̂���͂ɂ����̂ł���Ǝ������̂ł���܂��B
�������A���̕��͑��͂������ɑ傫�Ȃ��̂ł��邩���A���̎��ɁA��������Ď����āA
�u���͂Ƃ����̂͒n���Ȃǂɑ���̂�����ĉ��������A�P���C���Đ_�ʂāA���R�ɋ��s���āA�v�����ɗV�Ԃ��Ƃ��ł���悤�Ȃ��̂ł���B���͂Ƃ́A�l�Ԃ̒��ł���ԋ����ȗ�v���n�̒��ł��ł������ȃ��o�ɏ�����̂ł́A�l���n�����\�͂Ȃ��̂ł��邩��A����ł͋�s�͑S���s�\�ł���B�������A���̗�v�����o�ɏ�����̂ł��A�]�։��̍s�K�ɏ]���Ă����Ƌ���ɏ悶�Ďl�V���ɗV�Ԃ��Ƃ��ł���悤�Ȃ��̂ł���B�v
�Ǝ�����Ă���܂��B���̈Ӗ��́A�ɗV�Ԃ��Ƃ̕s�\�ȗ�v���A���̂悤�ɗV�Ԃ��Ƃ��ł���̂͑S���]�։��̗͂ł��邱�Ƃ�\�킵�āA��y�����̑S�̂����͂ɂ��Ƃ����Ӗ��𖾂炩�ɂ����܂������̂ł���܂��B
������A���a��t�̐����ꂽ���͂Ƃ́A��������͂�������Ƃ����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�O���̗͂͏������������A�S��������ɔ@���̊�͂ɂ�邱�Ƃ����������̂ł���܂��B
 �i�ˌk���E�a��̂��b�j
�i�ˌk���E�a��̂��b�j
��������A�ґ�����Ƃ������Ƃ́w��y�_�x����сw�����_���x�̕��͂ł́A�O���̍s������ł���Ǝ�����Ă���܂����A�e�a���l�͋��Ɉ���ɔ@���̉���Ƃ���A���̉�������̒��ɏ�y�^�@�̋��E�s�E�M�E�̑S�̂��܂܂�Ă�����̂��Ɛ�����Ă���܂��B���Ȃ킿�w���s�ؕ��ށx�́w�����x�̏��߂ɁA
�u�ނ�ŏ�y�^�@���Ă���ɓ��̉������A��ɂ͉����A��ɂ͊ґ��Ȃ�B��������ɂ��Đ^���̋��s�M����B�v
�Ǝ�����Ă���܂��B������A��y�^�@�͔@���̉����A�ґ��̓�̉���̑��͂Ȃ��A�^�@�̋��E�s�E�M�E�͑S����������̓��e���ڂ����������̂ł���܂��B
�������A����������̂ł͂Ȃ��A�얳����ɕ��̖�������������Ƃ���ɓ�̉���̈Ӗ�������̂ł���܂��B�w�������a�]�x�ɂ́A
�u�얳����ɕ��̉����
�����L��s�v�c�ɂ�
��������̗��v�ɂ�
�ґ�����ɋA������v
�Ǝ�����Ă���܂��B
�܂��A�u���̐��ŏO���~�ς̊��������邱�Ƃ��ґ�����v�ƌ����l������ƕ������A���l�̏�Ɋґ���������邱�Ƃ͋�����邩������܂��A�������g�̏�ɂ�������邱�Ƃ́A�e�a���l�̋��w�ł͋�����Ȃ����̂̂悤�ł���܂��B����́A�e�a���l�́A�u���g�̏�ɑP��������Ă�������̂��@���̉���ł���v�Ɗ����Ă���ꂽ�̂ł���܂��B�w�V�ُ��x�ɁA
�u�e�a�͒�q��l���������B���̌̂́A�䂪�v�炢�ɂĐl�ɔO���\�������������q�ɂĂ�����߁B��ɂ̌�Â��ɂ��Â����āA�O����\���l���䂪��q�Ɛ\�����ƁA�ɂ߂���r���̂��ƂȂ�B�v
�ƌ����āA��q��l�������Ȃ��Ƃ��\����Ă���܂��B���̈Ӗ����炢���A���Ƃ����l�ɖ@�`��`����悤�Ȃ��Ƃ�����Ƃ��Ă��A����͔@������̖����̊����ł����āA���̍s�������̂ł͂Ȃ��̂ł���܂��B
�܂��A���t�̈Ӗ����猾���Ă��A��y�ɉ���������̂��Ƃ��ґ��Ƃ�����ׂ��ŁA��y�ɉ������鎄�̏�ɔ@������̖����������Ă��������āA���ꂪ���̐l��M�S�ɓ������Ƃ�����܂��Ă��A����͑������v����@���̊����ł���܂�����A�ґ�����Ƃ����ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤�B
�@������̖����ɑ��̏O���������A���v��^���銈��������Ƃ������ƂƁA�ґ�����Ƃ������Ƃ́A�ꉞ��ʂ��čl���Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂ł���܂��B
 �i����Ǐr�搶�̂��b�j
�i����Ǐr�搶�̂��b�j
��y�̂��Ƃ��y�Ƃ����B
��y���ł���������Ƃɂ͖{�肪����܂��B��y�����̂��߂ɖ@����F�͎l�\��������Ă��܂��B�{��Ƃ�������N�����A����N�����āA�����Ɋ�s�Ƃ����āA����������邽�߂ɂ́A��͂�s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B������������邽�߂̍s���Ȃ��Ƃ��ɂ͊肪�������Ȃ��̂ł��B�@����F���{����N������āA���̖{����������邽�߂ɁA�����钛�ډi���̏C�s�����ꂽ�B����͉����Ȃ��������Ƃ����ƁA�u�Z�g�����̍s�v�ł���Ƃ��o�ɂ͏o�Ă��܂��B�V�e��F�́A
�u����͌ܔO��̍s���v
�Ɨ}���Ă�����B����������邽�߂Ɏ��H���Ȃ��ꂽ�B�s�͎��H�ł��B���̊�ƍs�ɂ���Č��ꂽ���E������y�ł��B������u��ƍs�ɕāc�v�Ƃ������t���g���B��������g���Ȃ�A������u�V��v�Ƃ����B��Ɋ�Â����Ƃ���̍s�A����ɕČ��ꂽ���E����y���Ƃ����̂ŁA����ŏ�y�̂��Ƃ��u��y�v�Ƃ������̂ł��B��y���ł����������̂́A
�u�{��ɂ���ĕ�y�Ƃ������̂��ł����������̂��B�v
�Ƃ������Ƃł��B
��X�̏ꍇ�ł��A��͂���Ă���킯�ł��B�������A��X�̏ꍇ�́A��ł͂Ȃ��ė~�Ȃ̂ł��B��͏����ł����~�͕s���Ȃ��̂ł��B�s���̂������Ƃ͍D���ŁA�s���̈������Ƃ͌����ȍ����ł��B�ł�����A�~�̏ꍇ�ɂ͍s�ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł����āA������ƂƂ����B�����ĕ���̂��ƕ�Ƃ����B�Ƃ̉ʕ����B������A�������̏Z��ł���̂��A��͂���̕�y�Ȃ̂ł��B������q�y�Ƃ����B�Ƃɕ���y�Ȃ̂ł��B�����������Ă���悤�Ȑ��E�ɏZ��ł���킯�ł��B
��y�̂ł������ƁA����͊�ł��B�����āA���ꂪ�ł�����������y�̓����A���̗������y�̈��ʂƂ����B����炷�ׂĂ��{��ɂ����̂�����A������u����Ȃ�ƌ����v�Ƃ����Ă���̂ł��B��y�̈��ʂƂ����Ă����邪�A���̕��͂��Ƃ͖{��B�{�肪�s����ꂽ���Ƃɂ���ď�y�����������B���̎���������y�Ƃ����̂́A��X�̉����ɉ����Ă���̂ł��B��y�͂�����y�ɉ������̂ł͂Ȃ��B��X�̉����Ƃ������A��������̂̌����ɏ�y�ɂ���ĉ�����ꂽ�B
���a��t���V�e��F�́w��y�_�x�����߂���鎞�Ɂw���ʎ��o�x�ɏƂ炵�ĉ��߂����B�w���ʎ��o�x�ɂ́A������㊪�Ɖ����A�㉺�Q��������̂ł��B�㊪�̕��ɂ́A
�u��y���ǂ����ďo���オ�������A�o���オ������y�͂ǂ����������������Ă��邩�v
�����������Ƃ������Ă���̂ł��B������A�㊪�̕��͔@���̏�y�ɂ��āA���̈��ʂ��ڂ��������Ă���B�����ĉ����ɂ́A
�u���̏�y����X�̑厖�Ȗ��ł��鉝���ɉ����Ă���v
�Ƃ������Ƃ����炩�ɂ��Ă���B���x�́A��X�̑厖�ȉ����̖��B�����ɂ���A��X�����̏�y�ɉ������邱�Ƃ��ł��邩�A�����������ł��B�ł�����������y�́A���łɂ����A��X�̉����̖���]���Ƃ���Ȃ������Ă���B�u���āA��X���A�����ɂ��Ă�����J���Ă������v�Ƃ�����肪������Ă���̂ł��B
�܂�A�㊪�̕��́A�@�����l�Ԃ������铭���ɂ��ďq�ׂ��Ă���B�����́A����Ɋ�Â��āA�l�Ԃ��������Ă����Ƃ������Ƃ����炩�ɂ���Ă���B�Ƃɂ����A���̂̌����ɐl�Ԃ̋~�����͂�����Ƒł��o����Ă���B�]���Ƃ���Ȃ��������Ă���B���������_�ŁA�u�^�������v�Ɛe�a���l�͋����̂ł��B���ꂪ�܂��y�̈��ʂƂ����ꍇ�̈��ʂł��B��y�̈��͖{��A�ʂ��܂��{��Ƃ������̂���X�̏�Ɏ�������A�������������������̂ł��B������A�����ʂ��{��B���ꂪ�u��y�̈��ʂ͐���Ȃ�v�Ƃ������Ƃł��B
�����āA
�u�ł�����������y�͂ǂ�ȓ����������Ă��邩�B�v
�Ƃ�������ǂ��A��y�̓����Ƃ����A����͖{����O���Ɏ������铭���Ȃ̂ł��B����ȊO�ɂ͂Ȃ��B���̒��ɁA��X�̏O���̈��ʂ������Ɗ܂܂�Ă���Ƃ������Ƃł��B���ׂĂ͖{��ł���B��y�̈����ʂ��A���ׂĐ���Ɋ�Â��B���͎��H�����ł��B�ʂ͎����B�ǂ��֎������邩�A�{�肪�ǂ��֎������邩�Ƃ����A�O���̏�ɁA�������̏�ɖ{�肪��������B���ꂪ��y�̓����B������u��y�̍s�v�Ƃ����܂��B��y�̑����̍s�ł͂Ȃ��̂ł��B��y�������B����ŏ�y�̍s�B�w���s�ؕ��ށx�ɁA�����������Ƃ��o�Ă���킯�ł���܂��B
 �i����Ǐr�搶�̂��b�j
�i����Ǐr�搶�̂��b�j
�얳����ɕ�����̉�����B���̐S�������������Ă��Ă���B���̐S����X�����̏O���̏�ɐU���������Ă���B�����e�a���l�́u�얳����ɕ��̉���́E�E�E�v�Ƃ����܂��B����͂܂������Ȃ�A�u�@������v�ł��B�@���̉���ɂ���āA��X�̉�����������藧�B�@���̉���ɂ��Ƃ���́A��X�̉����A�ґ��A���ꂪ��y�^�@�B
�����ŁA�@�R���l�́u�s����v�Ƌ��Ă���B�ʔ������Ƃ�������B�u����͗v��Ȃ��v�ƌ�����̂ł��B����܂ŁA����Ƃ����͈̂ꐶ�����@�����܂�q��A���邢�͌�����ς肵�āA������܂̕��U������邱�Ƃ������Ă����̂ł��B
�u������v�Ƃ����āA�����܂̌��邽�߂ɁA�ꐶ�����q��A���o��ǂ�A���邢�͌�����ς肵�āA������݂ȐU�������B������u����v�Ƃ������B�������ƁA���������̂��`���������̂ł��B�悭�A��c�։��������Ă����邱�Ƃ��u��c�ɉ������v�ƌ����ł��傤�B�u���o���c�։������B�v�ƌ����ł��傤�B��y�^�@�́u���o���c�։������v�ȂǂƂ������Ƃ͌����܂���B���o�́A��X�ɉ�����ꂽ���̂ŁA�������������Ȃ��B�Ƃ��낪�A��y�^�@�ȊO�́A������̋����ł́u���ɉ������v�Ƃ����B�ǂ����Ă����������l�����������Ȃ��̂ł��B�l�Ԃ��畧�։������Ƃ����A������������ł��B
�e�a���l�̍l���Ă���u����v�͂���ȉ���ł͂Ȃ��B����ɂ���Đl�Ԃ����藧�悤�ȉ���ł��B��X�̉���ɐ旧���ē����Ă������ł��B������u�{��͉���v�Ɖ��߂��ꂽ�B�@�R���l�́u����͗v��Ȃ��v�Ƃ���ꂽ�B�u�s����v�ł��B
�u���O���͕����܂ɉ��������̂ł͂Ȃ��B�����܂ɂ��O�����������ȂǂƂ����̂͐�����̍l�����A���͂��B�����ł͂Ȃ��B������s������B���O���͕����܂ɐU���������̂ł͂Ȃ��B�v
���������ł��B����Ȃ�u�ǂ��������̂��v�Ƃ������Ƃ́A�ǂ��������́A�܂��͂����茾�����Ă����Ȃ��B�������ɓI�ɁA�ے�I�Ɍ���ꂽ�����ł��B�@�R���l���������Ȃ��̂́A�����������ɐG��Ă����łɂȂ�Ȃ������Ƃ������Ƃ�����̂ł��傤�B
�����ɂ�͂�e�a���l�����o�܂��ɂȂ�Ȃ���Ώ�y�^�@�ɂȂ�Ȃ��Ƃ�����肪��������̂��Ǝv���܂��B
�e�a���l�́u�@������v�ƌ�����B�@�R���l�́u�s����v�ƌ�����B���̌��t�����ł͌����Ă��邱�Ƃ�������ƕ�����܂���B�u���������v�Ƃ���܂����A�u�얳����ɕ��͕����̂��v�ƁB�ǂ��ɂ���Ȍ��t������̂��Ƃ����A�w���ʎ��o�x�̉����̍ŏ��ɏo�Ă��܂��B�u�{�萬�A�̕��v�Ƃ����̂ł����A���̏�ɐ^�@�͐��藧���Ă���̂ł��B�l�\����̑�\����̏�ɐ^�@�����藧���Ă���̂ł͂Ȃ��̂ł��B����͏�y�@�ł��B�����̓n�b�L�����Ă����܂��傤�B
��\����A���S�M�y�̊�A�������b�ɂ��Đ��藧���Ă���̂͏�y�@�ł��B�e�a���l�̏�y�^�@�͖{�萬�A���̏�ɐ��藧���Ă���B�����ɑ厖�ȉ���Ƃ������t������B�{�萬�A�̌o���́A
�u������O���A���̖������ĐM�S���삹�ƁA�T����O����B���S�ɉ�������܂ւ�B�ނ̍��ɐ��܂��Ɗ肸��A���Ȃ킿�����āA�s�ޓ]�ɏZ���c�B�v
���������Ă���B�����Łu���S�ɉ�������܂ւ�v�Ɛe�a���l�͓ǂ�ł����܂��B����͐��l���Ɠ��̓ǂݕ��ł��B����ȓǂݕ��������l�͑��ɂ͂Ȃ��̂ł��B�w���ʎ��o�x��ǂl�͂�������B�P����t���@�R���l���ǂ�ł�����B����ǂ��A�u���S�ɉ�������܂ւ�v�Ƃ͓ǂ�ł��Ȃ��̂ł��B�u�T����O�܂ł����S�ɉ�����āE�E�E�v�Ɠǂ�ł���B
�u������āv�Ƃ����Ɛl�Ԃ�������邱�ƂɂȂ�B�u��������܂ւ�v�Ƃ����̂́A����������Ă�����B�������S�R�Ⴄ�B���A�e�a���l�́A�����ǂݔ����ꂽ�킯�ł��B�u���S�ɉ�������܂ւ�v�Ɠǂ܂ꂽ�̂��A���a��t�́w�����_���x�̎����Ƃ������A�w��Ƃ������A�����ɂ���Ă����������ƂɋC�����ꂽ�̂ł��傤�B
�����ɂ܂��A�u���S�ɉ�������܂ւ�v�Ɓw���ʎ��o�x���ǂ߂��B���̖ڂ������čĂсA�܂��w�����_���x��ǂݕԂ��ꂽ�B����ɂ���̊�ł���Ƃ���́w��y�_�x�́u�{��͉���v���u�@���̖{��͉���v�Ɠǂݔ����ꂽ�B�����������Ƃ�����̂ł��B
�@���̉���ɂ���āA��X�̉�����������藧�B�䂪�g�̎p���v���m�炳��āA�����ɑ傫�Ȉ�̓]�N����B������u��S�v�ł��B�����ɂ܂����p�Ƃ������̂��ł��������āA�@���ւ̈��������n�܂��Ă����B���ꂪ�������Ō����鉝������ł��B
�����āA�@������̂��Ƃ���a��t�́u���́v�ƌ�����B�e�a���l�́u�@������v�ƌ�����B���t�͈Ⴄ����ǂ��������Ƃł��B���a��t�́u���́v���邢�́u���́v�A���̗͂ƌ����܂��B���̕��̗͂Ƃ����̂́A�ǂ�������ԂŁA�ǂ����������ł��邩�Ƃ����ƁA����Ƃ������������Ă�����B�l�ԂɊ��т������������āA�l�Ԃ����o������A�����̎p�Ɏv���m�炳���B���ꂪ�@������̓����ł��B���ꂪ���́A���̑��͂ɂ���ĉ�����������藧���A�܂��A�ґ���������藧�̂��Ƃ������ƂȂ̂ł��B
 �i����Ǐr�搶�̂��b�j
�i����Ǐr�搶�̂��b�j
�厖�Ȃ̂́u����v�Ƃ������t�ł��B����͏�y�^�@�̐����Ƃ����Ă������B���̌��t���ɂ�����A��y�^�@�͐��藧���Ȃ��Ƃ����قǂ̂��̂ł��B�����u��y�^�@�͂ǂ������@�����v�Ɩ��ꂽ�Ȃ�A���́u����̏@�����v�ƌ����������炢�ł��B
���́u����v�Ƃ������Ƃ��ŏ��Ɍ������l�͓V�e��F�ł��B���ꂩ����a��t�̂Ƃ���ŁA�܂��u����v���o�Ă���̂ł��B���̂���l�ɂ����u����v�Ƃ������t������B�e�a���l���u��y�^�@�͉���̏@�����v�Ƃ������Ƃ��n�b�L���Ɖ�������ꂽ���Ƃɂ���̂��A��͂�A���̓V�e��F�Ɠ��a��t�ł��B���̂���l�ɂ���Đ^�@�̗v���n�b�L�������B�u����Ƃ������Ƃ���y�^�@�̗v���v�ƃn�b�L�����ꂽ�̂͐e�a���l�ł�����ǂ��A�V�e��F�A���a��t�̂���l���u����v�ƌ������ƂɐG��Ă����邱�Ƃ��肪����ɂȂ����B
�V�e��F�̂����t�Ƃ��Ắu�{��͉���v�Ƃ������t������B����́w��y�_�x�̏I���̂Ƃ���ɏo�Ă��܂��B������A�V�e��F�������������t�Ȃ̂ł��B�u�{��͉���v�ȂǂƂ������Ƃ͂ǂ��ɂł�����悤�Ɏv���̂�����ǂ��A�����ł͂Ȃ��B�����ɂ����Ȃ��̂ł��B�Ƃ��낪�A�V�e��F�̏ꍇ�A�u����v�Ƃ����̂́A�ǂ����܂��e�a���l�̂悤�ɂ̓n�b�L�����Ă��Ȃ��̂ł��B�w��y�_�x�ŁA���́u����v�Ƃ������t�̏o�Ă���̂͌ܔO��̂Ƃ���ł��B���̏I���Ɂu����v�Ƃ������t���o�Ă���B
�u��q�v�A�q�ށB
�u�]�Q�v�A�����ق߂�B
�u���v�A�肢�����B
�u�ώ@�v�A�悭���ɂ߂�B
�����āu����v�A������O���ɐU�������A���̌������O���ɗ^����B
���������̂��u����v�ł��B���������Ƃ������Ƃ��猾���A�u����v�Ƃ����͎̂����̐ς������O���ɗ^����A�U�������B���̎��������Ƃ������Ƃ�����Ώ�y�ɐ��܂�邱�Ƃ��ł���B�V�e��F�́A���������T�̎��H���F�ǂ��Ƃ��Đ����ꂽ�̂ł��B������A���̏ꍇ�̉���́A���ǁA��F�̖{��͉���ł��B�����͂܂��u�@������v�Ƃ����悤�ȂƂ���܂Ńn�b�L�����Ă��܂���B
���ŁA���a��t�́A���́u����v����ɕ�����ꂽ�B�w�����_���x�̒��ŁA�V�e��F�̉�������グ�āA
�u����Ƃ������̂ɂ͓��ނ���B��ɂ͉����A��ɂ͊ґ��v
�ƁA���������ӂ��ɓ�ɕ����Ă�����B�u�ґ�����v�Ƃ����悤�Ȍ��t���͂��߂ē��a��t�ɂ���Ďg��ꂽ�̂ł��B�������A���a��t�ł��A�܂��A�����n�b�L���Ƃ͂��Ă��Ȃ��B������n�b�L�����ݎ�����l���e�a���l�Ȃ̂ł��B
��X���q�y�ɂ���킯�ł��B�q�y�̈�Ԃǂ�l�܂�͎O�����ł��B�O�����̂ǂ�l�܂�͒n���A�q�y�̏���͐l�E�V�ł��B��X�͐l�ł�����A�q�y�ɂ͋��邯��ǂ��A�܂��O�����ł͂Ȃ��B�����ŁA������̕����Ƃ������̂����ɂȂ�̂ł��B��T�̐l�Ԃ́A���̖ڂ��炲���ɂȂ�ƁA�n���̕��������ĕ����Ă���炵���B������u���]�։�v�Ƃ����B�u�f�v�u�Ɓv�u��v�̎O���Ƃ����܂��āA��X�͖����S���N�����ł��傤�B���ꂪ�f�ł��B�f�Ƃ����͔̂ϔY�ł��B�����āA�v��Ȃ��Ă��������Ƃ��v���B�Ƃ�ł��Ȃ����Ƃ��v���B�����S���N�����Ă͋Ƃ����B����������s�������肷��B�Ƃ̌��ʋꂵ�ށB�ꂵ��ŁA�܂������B������O���Ƃ����܂��āA�s�b�`���A�s�����֍s���Ƃ����̂��u���v�ł��B����ɂ͗�O���Ȃ��B����ŋꂵ�ނ̂ł��B�Ƃ��Ă͋ꂵ�ށB�ꂵ��ł܂������B�����ċƂ�B�܂��ꂵ�ށB�����������Ƃ��J��Ԃ��ăO���O������Ă���B�������A����͓����Ƃ��������Ă���̂ł͂Ȃ��̂ł��B����ꂵ�݂��[�܂�B����ꂵ�݂̐��E�߂Â��Ă���̂ł��B
���̖ڂ��炲���ɂȂ�A�l�Ԃ̎p�͂����������̂Ȃ̂ł����A��X�͒��X�����͎v��Ȃ��B���]�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��v�킸�A�������Ă��ꂪ���W�Ȃ̂��Ǝv���Ă���B�Ƃ�ł��Ȃ��b�ł��B���̖ځA���ꂪ�l�ԂƂ������̂����������Ƃ���̒q�d�ł��B�l�Ԃ̖{���̎p�����������q�d�����t�ɂȂ��Ă���̂��u�얳����ɕ��v�Ȃ̂ł��B������A�u�q�d�̔O���v�Ƃ����B�q�d�Ƃ����̂́A���̂��������͂̂��Ƃł�����A�O���ɏƂ炳���Ƃ����ƁA�l�Ԃ̖{���̎p���n�b�L������̂ł��B�����łȂ���Ύ����ŋC�����Ƃ������Ƃ͂���܂���B���O���͋��ł��B�l�ԂƂ������̂����������q�d�̋��A���ꂪ�얳����ɕ��ł��B
��̓I�ɂ́A����́A��X���������Ƃ����`�Ŏ���Ă����̂ł��B�������Ƃ������Ƃ́A�S���A�얳����ɕ��̂����ł�����A�O�������������Ƃ������Ƃ͋������Ƃ������ƂɂȂ�B�u���������v�Ƃ����āA�u�����v�ȊO�ɂȂ��B���������Ƃɂ���āA�������g�̎p���n�b�L�����Ă���̂ł��B�u�Ƃ�ł��Ȃ�����������Ă������ȁv�Ƃ������ƂɃn�b�ƋC�����B���ꂪ�厖�Ȃ̂ł��B
���������䂪�g�̎p���Ƃ炵�o���Ă����B���ꂪ�얳����ɕ��������Ƃ������ƂȂ̂ł��B������A�얳����ɕ��̓����̂��Ƃ��u�����v�Ƃ������܂��B�����͂ǂ��������������邩�Ƃ����ƁA���Ƃ������̂�m�点��Ƃ�������������B�䂪�p���v���m�点��Ƃ����������얳����ɕ��̓����ł��B���ꂪ�����Ȃ̂ł��B���̂��Ƃɂ���āA���߂Đl�Ԃ͂������������ɕ����Ă����Ƃ������ƂɋC�����̂ł��B�Ƃ�ł��Ȃ������ɕ����Ă����Ƃ������ƂɋC�����̂ł��B�S������y�ɔw�������ĕ����Ă���A�����̕��ւƍs���Ă���B�������������̎p��������ʂ��āA�얳����ɕ��������������Ƃ�ʂ��Ďv���m�炳���B���ꂪ�u���������v�ł��B�䂪�g���v���m�炳���B�v���m�����S��M�S�Ƃ����B
�u���������A�M�S����v
�u���v�̎��ɕK���u�M�v�Ƃ������̂��o�Ă���B�u���v�̂Ƃ���ɐ��藧�̂��u�M�v�ł��B���̎��ɁA��̑傫�ȓ]�N����̂ł��B�l�ԂƂ͂����������̂ł��B
�Ⴆ�A�������C�Ȃ��ɕ����Ă���ł��傤�B�����������A�ˑR�A
�u�����A�t���܂ɗ��Ă������B�v
�ƁA�n�b�ƋC�������Ƃ�����B
���͂��̂���A���̂����ɂT�炢�V�����œ��̕��ɍs���Ă��܂��B�Ƃ��낪�A���܂ɐV�_�˂Ƃ��P�H�Ƃ��֍s�����Ƃ�����B�Ƃ��낪�A�������肵�Ă���̂ł��B�����͓����s���̃v���b�g�z�[���֍s�����̂ł�����A�����֍s���v���b�g�z�[���łȂ���Ȃ�Ȃ��̂ɁA�����ŋC�����Ȃ��̂ł��B�����s�̃v���b�g�z�[���������ĕ����Ă���B�ꐶ�����K�i���オ���Ă���B�r���Ńn�b�ƋC�����A
�u���炢����A�t���܂ɗ��Ă������B�v
����ŁA�܂����֍~��čs���܂����A�ʔ������̂ł��B
�n�b�ƋC�������r�[�ɑ������܂��B���o�̗͂Ƃ����̂͂��炢���̂ŁA�]����N�����Ă���̂ł��B���ł��������Ǝv���܂��B���C�Ȃ��ɕ����Ă����āA�u����͔��̕����������Ă���ȁv�ƋC�������r�[�ɑ��̓N���b�Ɖ���Ă��܂��B�C�����āA����ł��A�Q�����R�����S�����c�ƕ����̂͂ǂ������Ă��܂��B�����A�C�������r�[�ɃN���b�Ƒ��������B�܂�A�����ɓ]�N����B�u�t���܂ɕ����Ă����v�ƋC�������Ƃ��厖�Ȃ̂ł��B���ꂪ������Ȃ���Γ]��͋N����܂���B���o�ɂ͕K���u��v���N����B���������̂��u��S�v�Ƃ����B�����ɓ]��ƂƂ��ɁA���x�͋t�̕����Ɍ������Ă̕��݂��n�܂�B������u���v�Ƃ����B����Łu����v�Ȃ̂ł��B
�O�����Ɍ������ĕ����Ă��������A��y�ɐU������Đi�߂��Ă���B������u��������v�Ƃ����B��y�֍s���Ƃ����Ӗ��ł��B����������Ƃ����̂ł��B�����Ƃ����͉̂�������Ƃ������ƁA���������ӂ��Ƀn�b�L���Ɛe�a���l�̎g���Ă����錾�t�ʼn������Ă����Ȃ��ƁA�����Ƃ����̂́A�����u���̐ꂽ���Ƃ��v�Ȃǂƍl����̂ł��B�u�^���̋��E�s�E�M�E�Ƃ����̂͏�y�ւ̓��ł��B��y�ւ̓��s���A
�u�����ɋ�����A�s����A�M����A����B�v
�Ƃ������Ƃ��A�����������Ƃ������Ă�����B
���̉�������Ƃ������Ƃɂ��ẮA���a��t�̋����Ɏ�������ꂽ�̂ł��B���a��t�͂��̂悤�Ȃ��Ƃ܂ł̓n�b�L����Ȃ���������ǂ��A��͂�u����v�������Ɗґ��ɕ�����ꂽ�Ƃ������Ƃ́A���ɑ傫�Ȍ��т��������B���a��t�̎w���ʂ��āA�͂��߂Đ^�@�Ƃ������̂��m�������̂ł��傤�B
 �i����Ǐr�搶�̂��b�j
�i����Ǐr�搶�̂��b�j
�u���҂̉���͑��͂ɂ��v
�ƁA�u���ҁv�Ƃ���܂����A�u���v�Ƃ����̂͂���y�������Ƃ������Ƃł��B���ꂩ��A�u�ҁv�͎�����������y�������ƁA����y�̌��������������Ƃ��ł���B���̌�����ɗ͂ɂ��āA�܂��t�ɁA�����鐶���̐��E�ցA�q�y�Ƃ����Ă������ł����A�����֗I�X�Ɛg�𓊂��o���Ă�����B��y�����Ƃɂ���ď�y�̌������������B��y�̌������������ƁA�����͂ɂ��Ė����̐��E�g�𓊂��o���āA���ŋ�J���ł���Ƃ������Ƃł��傤�B������u�ґ��v�Ƃ����B�����͉������A�ґ��͊҂��Ă��鑊�B���O�������������Ƃ���ɁA���̓�����藧���Ă���B���ꂪ��y�^�@�ł��B
�u�ނ�ŏ�y�^�@���Ă���ɓ��̉������B��ɂ͉����A��ɂ͊ґ��Ȃ�B�v
���̉��������B��͉�������A���ꂩ��ґ�����B��y�����̂������Ƃ����̂ł��B��������o�ł́u�����v�Ƃ����B���������B�Ƃ��낪�A���̂���y�����Ƃ����ƁA���x�͏�y�̌��������Ă���B���̌����͂ƂȂ�̂ł��B�����āA�I�X�ƌ������A���邭�ƌ������A�����̐��E�ɐg�𓊂��o���ċ�J���ł���B���ꂪ�ґ��ł��B���̓�����藧�̂���y�^�@���ƁB
���āA�ґ�����Ƃ������Ƃ̊���A������o�̒��ɂ���܂��B�ґ�����Ƃ������t�͂Ȃ��ł�����ǂ��A
�u�����̐��E�ɐg�𓊂��o���Ă�����悤�ȗ͂�^���Ă�肽���B�v
�Ƃ����͕̂����܂̊肢�̈�ł��B���Ɏl�\����ƌ����Ă���܂����A���̂Q�Q�Ԗڂł��B���\���ɂ́A
�u�����鐶���̐��E�A��J�̑������E�ɗI�X�Ɛg�𓊂��o���āA���邭��J���Ă�����悤�ȁA���������S��^���Ă�肽���B�v
�Ɛ����Ă���B�������a��t�������Ă����āA�ґ�����Ƃ������Ƃ�����ꂽ�B�����ŁA���̊ґ�����Ƃ����̂́A�����̐��E�A����������̐��E�A��J�̐₦�ʐ��E�A�����������E�g�𓊂��o���Ă����Ƃ������Ƃł�����A��͂��̐����̌`���̂�킯�ł��B�{���ɏ��������Ƃ������Ƃ͂ǂ��������Ƃ��B�{���ɏ��������Ƃ������Ƃ́A
�u������Ȃ����E�ɐg�𓊂��o���Ă�����B�v
�Ƃ������Ƃ��{���ɏ��������Ƃ������Ƃ��ƁA����������̂ł��B�u��J�����₾�v�Ƃ����̂�������A����͏����������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B�u�ǂ�ȋ�J�����Ă��悢�v�Ƃ����̂��{���ɏ����������Ƃł��B
�Ⴆ�A�~�A�R�^�c�Ȃɓ����Ă��܂��ƁA�O�֏o��̂������Ăǂ��ɂ��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ��������֏o���Ȃ��B�������֏o���Ȃ��Ƃ����̂́A����܂�g�̂��������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��傤�B���͊e�ƒ�ɕ��C������܂�����A���܂肻���������Ƃ������܂���ǂ��A�̂͂悭�K���֍s�������̂ł��B�~�̊������ɑK���֍s���āA
�u��������A����Ɖ����낤�B�v
�Ǝv���Ē������Ɠ��ɓ����āA�悭�̂����߂Ă���O�֏o��B���C���ɗ₽�����֏o��̂ł�����ǂ��A���̎��ɂ́A�����A�₽������ɂȂ�܂���B�������ċC�����������悤�Ȋ����������܂��B����͐g�̂���قlj���������ł��傤�B�g�̂��{���ɉ�������A���X�₽�����E�֏o�����čs���Ă��A�ǂ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B�����A�������ĉ������̂������܂��B
����Ɠ����Ȃ̂ł��B�{���ɏ���������A�{���ɏ��������Ƃ����̂���������ł����A�{���ɏ���������A���̗͂ŏ�����Ȃ����E�A��J�̂��܂Ƃ����E�A���������Ƃ���֖��邭�g�𓊂��o���āA�����Ċ��ŋ�J���ł���B�����Ȃ��Ă����{���ɏ��������̂��B�����������Ƃ��������Ă���̂ł��B������A������Ȃ����E�֗I�X�Ɛg��u���Ă�����̂́A����������̗��v�Ȃ̂ł��B������Ȃ��܂܂ɁA����ȋ~����Ȃ����E�֏o�����Ă����킯�ɂ͍s���܂���B���ꂽ���ē��ꂽ���Ďd�����Ȃ��̂ł��B�{���ɏ�����Ƃ����̂́A�t�ɁA�����̐��E�g�𓊂��o���Ă�����B
�����ł́A�̂��琶���Ƃ������̂ɂ͓��ނ���Ƌ������Ă��܂��B��́u���i�i�Ԃ�j�����v������́u�ψՁi�ւ�₭�j�����v�B
�u���i�����v�Ƃ����̂́u�悩�����A���������v�u�悩�����A���������v�ƁA�����L���L���ς���đ����Ȃ��̂������̂ł��B���ɂȂ��đ����Ȃ��B�����ċ�J�ɐU���ċ���������������A���邢�͂܂��A��s�����ڂ�����A�������������肵�Ȃ��琶���Ă���悤�Ȃ̂��u���i�����v�Ƃ����B���ꂩ��u�ψՐ����v�Ƃ����̂́A���������Ȃ̂�����ǂ��A�Ӗ����ς���Ă����Ƃ������̂̂��Ƃł��B�����ɂ͈Ⴂ�Ȃ��B��͂��J�����܂Ƃ��̂ł�����ǂ��A�Ӗ���������ƈ���Ă����B���������̂��u�ψՐ����v�Ƃ����̂ł����A�������ґ�����Ƃ����̂́u�ψՐ����v�̂��Ƃł��傤�B�u���i�����v�Ȃ�ꍏ�������������瓦���o�������̂ł��B�����ł͂Ȃ��ɁA�ґ�����͊��Ő����̐��E�������Ƃ����̂ł�����A����́u�ψՐ����v�̕����Ǝv���܂��B
���˂��ˁA�u�����ɓ�킠��B��ɂ͕��f�����A��ɂ͕ψՐ����v�����A�ǂ��������̂Ƃ��낪�Ȃ��Ȃ����_�������Ȃ��������u���ǂ�v��H�ׂȂ��炦�炢���Ƃ��v���o�����B�܂�A���͂��̎��ɂ����v�����B
�u�f���ǂ�ɓ�킠��B��ɂ͕��f�f���ǂ�A��ɂ͕ψՑf���ǂ�B�v
����A�ǂ��ł����B�u�f���ǂ�v��H�ׂ�l�ɓ��ނ���̂ł��B����͉����Ƃ����ƁA��͖{���Ɂu���ǂ�v�̍D���Ȑl�B������A�V�w������ꂽ�藑�𗎂Ƃ����肵����A�����A�u���ǂ�v�̖���䖳���ɂ��Ă��܂��B������u�f���ǂ�v����Ԃ����̂��ƁB���������l���u�f���ǂ�v��H�ׂ܂��B���A���̐l�������H�ׂĂ���B���ꂪ�u�ψՑf���ǂ�v�ł��B
�u�f���ǂ�v��H�ׂ�l���������ނ���B����͂����̂Ȃ��l�B����͂�ނ��H�ׂĂ���B������́u���i�f���ǂ�v�ł��B�����u�f���ǂ�v�ł��A�����ԈႤ�̂ł͂Ȃ��ł����B����́u�f���ǂ�v�����ŐH�ׂĂ���̂ł��B�����Ȃ�����A��ނ��H�ׂĂ���̂Ƃ͂�����ƈႢ�܂��B������͋��������H�ׂĂ���B�O�Łu�V�w�����ǂ�v��H�ׂĂ���l�����߂��������ɂ݂Ȃ���u�f���ǂ�v��H�ׂāA
�u�����A��Ȃ��B�v
�Ƌ�s�����������Ȃ�悤�ȐS�Łu���ǂ�v��H�ׂĂ��܂��B�����Ƃ��u�f���ǂ�v�ɂ͕ς��͂���܂���B�u�f���ǂ�v�͉��ɂ��ς��Ȃ��B�u���ǂ�v�D���̐l������Ƃ����āA�ʂɁu�f���ǂ�v�̒l�i�������킯�ł��Ȃ����A�������Ȃ�����u�f���ǂ�v�����H�ׂ��Ȃ��Ƃ����āA�����Ă����킯�ł��Ȃ��B�S�������u�f���ǂ�v�ł��B����ǂ��A���̖��͑S�R�Ⴂ�܂��B
���f�����ƕψՐ����̏ꍇ������Ɠ����ł��B�l���̋�J�̖�������Ă���̂ł��B���Ő����̐��E�ɐg�𓊂��o���B���ꂪ�ґ�����ł��B�S�R�Ӗ����ς���Ă���B�����Ȃ�A��J�̖����ς��B�����ɂ͋�J��ʂ��āA�����������Ȃ���̖��킢�Ƃ������̂��o�Ă���B�l���̖��킢�ł��B
�e�a���l�́A����y�̌��������������A���ꂪ��̗͂ƂȂ��āA�����ċ�J�̐₦�ʂ��̐��ԂɎ����̐g�𓊂��o���āA���ŋ�J�̂ł���悤�ɂ��Ă�������Ƃ���ɁA�䂪��y�^�@�Ƃ������̂̋���������̂��Ƃ������Ƃ��n�b�L���Ɖ�������ꂽ�̂ł��B
 �i����Ǐr�搶�̂��b�j
�i����Ǐr�搶�̂��b�j
��\���Ƃ����̂́A��y���������Ƃɂ���Đ���������A�܂������ɁA��y�̌������̐l�Ԃ̏�ɋP���A�����ē����ɁA���̌������^�����Ă���B��y�������͉̂����ł��B��������B���͂ɂ���ĉ�����������藧�B
��y�̌��𗁂сA�܂��A��y�̌������^�����āA��y�ƌ��т��Ȃ���ꑫ�ꑫ��y�������Ă䂭�B�����������Ƃ���a��t�͉�������Ƃ������t�Ŗ��炩�ɂ���Ă���B�܂���\����ɂ���Ė��V�Ƃ����A���̂܂܂Ƃ����A��̂����������A�����B���̗͂ɂ���Ė��V�Ƃ������̂��^������B�܂������ɁA��\���ɂ���ĉ��������藧���āA��y�̌��Ƌ��Ɍ������^������B�q�y�����y�������̂������ł��B�q�y�ɂ����Ƃ��ɂ͏�y�Ƃ������̂́A����͑S���A�����A�f��݂����Ȃ��̂�����܂��B�f�����Ă�����̂�����B�q�y�����y�ւƂ����ꍇ�́A���̒f����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�Ƃ��낪�A��x��y�ƒ�������Ȃ�A����ɂ���Ă܂����V�Ƃ������̂��g�ɂ��A��y�̌��ƌ������^�����邱�Ƃ�ʂ��āA���x�͋t�ɁA�����鐢�E����y�łȂ����̂͂ǂ��ɂ��Ȃ��Ƃ������i�������j�ɂȂ�̂ł��B�q�y�̏�y�̒��ɓ��荞��ł���B�q�y����s���ƒf�₪���邯��ǂ��A��x��y�ɁA���̒f����Ď��蒅�����Ȃ�A���x�́A��y�Ȃ炴��͂Ȃ��B�q�y�͐����̐��E�ł����A�����̐��E�����ς̐��E�̒��ɕ�܂�Ă���B��y�Ȃ炴��͂Ȃ��B���������Ƃ���ɁA���x�͊��ŁA�����q�y�Ɍ������B���ꂪ�ґ�����ł��B
���͂ɂ���ĉ�����������藧�����B��������ƁA�����ɂ܂��A�����ɑ��͂ɂ���Ċґ�����Ƃ������Ƃ����藧���Ă���B�ґ��Ƃ����̂��q�y�������S�ł��B�q�y���̂Ăď�y�ւƌ������B�q�y���̂Ăď�y�������̂�����ǂ��A�����ɁA��y��Ȃ���q�y����y���Ɋ܂܂��B�����ɁA���x�͊����q�y�̒��ɐg��u���A�����������ʂ���o�Ă���̂ł��B���ꂪ�����Ă���̂����\���ł��B
�ґ�����Ƃ����̂́A�����������邾���ł͂Ȃ��A�l��������Ƃ������A�������������S�������̂ł��B���������悯������Ƃ����̂ł͂Ȃ��B����������������A��͂�l�������悤�Ƃ����S�ɓ��������B���̐S�ɐG��邱�Ƃ�ʂ��ď�y�������A���̐S�ɐG��邱�Ƃ�ʂ��ĕ��̐S�ɓ�������Ă���Ƃ������Ƃ��N�����Ă���B���������S���N���������Ƃ��{���ɍK���Ȃ̂ł��B������Ƃ������Ƃ́A���̊�Ƃ������̂ɐG��āA����ɓ�������Ĕ@���̊�ɁA�q�y�ɂ����Đ�����ƁA�����������ƂɂȂ�B������A��ɐ�����Ƃ����̂��q�y�������A�ґ�����̐S�ł��B
�}�v���M�S���N�����Ȃ�A�����ɖ��V�Ƃ������E���J����Ă���B���V�Ƃ����͉̂����Ƃ����ƁA���������̂܂ܟ��ς��Ƃ������ƁA������ґ��ł���̂ł��B�܂�A�q�y�����V�ł���Ƃ����̂ł��B��y���q�y�����V�ł���悤�ȐS�������Ȃ���A�ґ��Ƃ������Ƃ͐��藧���܂���B��y�̐S�͖��V�ł����A��y�̐S�������A�ǂ�Ȑ��E�ւ��ґ��ł���A�����鐢�E����ł���悤�ȁA���������S���^�����Ă���Ƃ������Ƃł��傤�B
�ґ��Ƃ������Ƃ́A�l�Ԃ̈ӎu�Ŋґ����悤�Ƃ����A�����������̂ł͂Ȃ��̂ł��B�ނ���A������O�ꂳ���邱�Ƃɂ���āA����ґ��Ƃ����悤�Ȍ`���Ƃ��Ă���̂ł��傤�B�ґ��Ƃ������͈̂ӎ��I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�m�炸�m�炸�ɓ�������Ă���Ƃ����A�����������Ƃ�����B
�}�v�̏ꍇ�͎����ɓO�ꂷ��̂��ƁB�����ɓO�ꂷ��A��������ɓO�ꂷ��A��������Η����ł͂Ȃ��A������������B�����Ƃ������Ƃ��N�����Ă���B������������B���𗘂����Ƃ����悤�Ȉӎ����āA�����Ƃ��āA�����Ƒ����������Ă���B�l�������悤�Ƃ����悤�Ȉӎ����Đl��������B
�����܂Ȃ痘���͂����Ɛ��A����B�����͕��ɂ����Ȃ��B�}�v�̉�X�ɂ͗����͐��藧���Ȃ��B�������������Ă����Ƃ������Ƃ��A���ꂪ�܂��A�������̂����珕����悤�ȓ��������Ă��āA�����������鑊�ɂ���đ��̐l���������Ă����Ƃ����A�����������Ƃ����藧�A���ꂵ���Ȃ��̂ł��B
�ґ��͊�Ƃ��Ă���B����͔��ɑ厖�Ȃ��Ƃł��B�ґ��Ƃ�����������Ȃ���A����Ȃ��̂͌l��`�Ƃ������A������`�̕����ɓ]�����܂��B������̂�����ǂ��A���̊��{���ɑS�������������牝������ɓO����B��������A���𗘂��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ă��A���̑��ɂ���đ�����������B���̏������Ă������̑��ɂ���đ����������Ă����B����������̂ł͂Ȃ��B�����������Ă����B�ґ��Ɏ���o���̂ł͂Ȃ��A�ґ��͊�Ƃ��Ă���B��͎����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����āA���̊���������邽�߂ɂ͉����ɓO����B���ꂵ���Ȃ��̂ł��B
��y�^�@�͕����ł���Ƌ��ɁA�����ɕ�F�����Ƃ������Ƃ���a��t�����炩�ɂ��ꂽ�B�ґ��Ƃ������Ƃ����ɂȂ�͕̂�F�Ȃ̂ł��B
�u�����A�����c�B�v
�ƁA���������������Ă���ƌ������ꂵ�Ă��܂��B��F���Ƃ����Ƃ���Ɍ�������ł���̂ł��B
 �i����Ǐr�搶�̂��b�j
�i����Ǐr�搶�̂��b�j
�e�a���l�́w���M��x�̏��߂̕��ɁA
�u�{��̖����͐���̋ƂȂ�v
�ƁA�u���̂��S�ɂ���Ăł����������������A���O���́A��������������ΕK��������v�Ƃ����ӂ��ɋ��܂��B�Ƃ��낪�A
�u���O�������������Ă�������Ȃ��B����͈�̂ǂ��������Ƃ��B�v
�����ɂ͂��O�������������Ă�������Ȃ��������A�l�Ԃ̂Ƃ���Ɉ����̂ł��傤�B���̉��������Ɨ}���Ă���B���Ƃ����̂́A���ł�������������Ƃ����̂ł��B�Ⴆ�A���̂������鎞�Ɏ�͈�ł��B�卪��������̂Ɏ�͈�ł��傤�B����ǂ��A��������܂��B����������܂��B�엿������B�F�X����܂��B���ꂩ�璎�����Ȃ��Ƃ������Ƃ����ɂȂ�B���邱�Ƃ��Ȃ����Ƃ��A�����Ƃ����Ȃ���A�킪�����炠���Ă��Ȃ��Ȃ��卪�͐����܂���B����ǂ��A��������̎킪��������A��ɐ����܂���B
�u���̂��ƈ���Ȃ������A�����ʖڂ��B�v
�Ƃ����u���̂��ƈ�v�́A��͂���ł��B���������厖�Ȗ{���̍��{�ł��B��X��������{���̍��{�ł��B�����ɉ�X���~�����O�����^�����Ă��Ă��A���̈�_��������������ǂ����悤���Ȃ��Ƃ��������������āA
�u����̈��͂����M�S�Ȃ�v
��������ꂽ�B�u���O���ɋ������珕����v����͊ԈႢ�Ȃ��̂ł��B����͊ԈႢ�Ȃ��̂�����ǂ��A�M�S�Ƃ�����_����������A���͂��ɉ�X��������O�����A������O���ɂȂ�Ȃ��Ƃ����A���̗v���������Ă���ꂽ�B
�u����̋Ɓv�Ƃ����Ƃ���ɓ��a��t�͖���������ꂽ�̂ł��傤�B���ꂪ�w�����_���x�̏��߂̕��ɁA���⎩���Ƃ����`�ŏo�Ă��Ă���̂ł��B
�u�������V���i�ނ������j�@���̌��������ʂł����ď\���̍��y���Ƃ炵�ď��i�����j���Ȃ��Ƃ����Ȃ�A���̛O�k�ɏZ��ł���l�Ԃ��A�ǂ����Ă��̌������������Ȃ����Ƃ����낤���B���ł��A�ǂ��ł��A�ǂ�ȏ�Ԃɒu����Ă���l�Ԃ����Ƃ炷�Ƃ����̂�����A����Ȃ�O�k�ɂ���l�Ԃ��݂�ȏƂ炳��Ă���͂����B�Ƃ炳��Ă��Ȃ��҂͈�l�����Ȃ��͂����B�Ƃ��낪�A����ɂ�������炸�E�E�E�B�v
�ƁA���a��t�͖����o���Ă�����B�������Ƃ炳��Ă��Ȃ��A�����͏Ƃ炳��Ă��Ȃ��Ƃ����̂ł͂Ȃ��ɁA���Ȃ��Ƃ��A�������g���Ƃ炳��Ă��Ȃ��B������������������B��������ƁA����͂Ђ���Ƃ�����A
�u��������Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�v
�u���ɏ�肪����̂ł͂Ȃ����B�v
�u���ɖӓ_������̂ł͂Ȃ����B�v
���������ӂ��Ȗ₢�������֓����o���Ă�����̂ł��B�����Ă��̎��ɁA���̖₢�ɑ��Ď��瓚���Ă�����B
�u�����Ă��킭�A�V�i�����j�͏O���ɑ����B�v
�����ł͂Ȃ��A�V�͏O���ɂ���B�Ƃ炷���ɊV�͂Ȃ��B�Ƃ炳��Ȃ��҂ɊV������ƌ�����̂ł��B��X�̕��ɑ���^���Ƃ������̂́A�������������Ƃ���֏o�Ă���̂ł��B�u�����܂̌�������Ȃ��̂ł͂Ȃ����v�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��A���A�ӂ��Ǝv���B�����������Ƃ���a��t�͐����ɍ������Ă�����̂ł��B
�u���ꂾ�����@���Ă���̂ɁA�����Ƃ��������Ă��Ȃ����A�����܂�����Ȃɗ͂��Ȃ��̂��ł͂Ȃ����ȁB�v
�ƁA�ӂƏo�Ă���B����ɑ��āA
�u�����Ă��킭�A�V�͏O���ɑ����B���̊V�ɂ͂��炴��Ȃ�B�v
�ƌ����Ă�����B�������ɖ�肪����̂ł��B
�����ŁA����ɂ��Ă̗Ⴆ���o���Ă�����B���߂̗Ⴆ�́A
�u�Ⴆ�A�����l�V���Ɏ��˂���ǂ��A�ӎ҂ɂ͌������邪�@���B�����̎��˂��炴��ɂ͂��炴��Ȃ�B�v
���z���W�X�Ƃ��Đ��E�����Ƃ炵�Ă��邪�A�ڂ̕s���R�Ȑl�ɂ͌����Ȃ��B���������Ⴆ�ł��B����ƁA���z�����E�����Ƃ炵�Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B�S���E���Ƃ炵�ē��邪�A�ڂ̕s���R�Ȑl�ɂ͌����Ȃ��B��������A����͌����Ȃ��l�̕��ɏ�肪����Ƃ������Ƃł��傤�B
�܂��A������̗Ⴆ�́A
�u���_�i�݂���j�̂������ɒ����ǂ��A��i�����j�ɂ͏��킳���邪�@���B�J�̏��킳����ɂ͂��炴��Ȃ�B�v
���_�Ƃ����̂͌ł܂��Ă���_�A�J�_�ł��B�Ƃɂ����A���̌ł܂����_���J�ƂȂ��ăU�[�b�Ɖ��֍~���Ă���B�Ԏ��𗬂��@���ɍ~���Ă����J�ł��B�J�̓W�����W�����~���Ă���B���E��������͂��܂����Ǝv���قǁA���̂����������ō~���Ă���B���������J�̗Ⴆ�ł��B����ǂ��A�ɂ͟��ݍ��܂Ȃ��B�ǂꂾ���J���~�������Đɂ͐�ɟ��ݍ��܂Ȃ��B��Ƃ����̂͌ł��Ȃ��Ă���̂��Ƃł��B
����͉�X�̐S��Ⴆ�Ă���̂ł͂Ȃ��ł����B��قǂ̖ӎ҂Ƃ����̂���X�̐S��Ⴆ���̂ł��傤�B�S�̖��ł��B�ڂ��s���R�Ȏ҂����畧�̌��������Ȃ��B���͏Ƃ炵�Ă����邯��ǂ��A�����S���[�����߂ɕ��̌��ɋ����Ȃ��Ƃ������Ƃł��傤�B�������̐ӔC�A�Ƃ炳��Ă��Ȃ��҂̐ӔC�A������u�V�͏O���ɑ����v�Ƌ����̂ł��B
��Ƃ����͉̂���Ⴆ�Ă��邩�Ƃ����ƁA���a��t�͉䎷�Ƃ������̂���ƌ���ꂽ�B�l�Ԃ̌����ł������S�ł��B�u�킵���E�E�E�v�u�N�����Ƃ������ƁE�E�E�v�ƌ����Ċ撣��܂��B�撣��S�A���������S��ɗႦ�Ċ�Ƃ����̂ł��B��ŁA�������ȂȐS�ł��B���������A������䎷�̐S�A�������撣��S�ɂ͕��̐S�����ݍ��ނƂ������Ƃ͂��肦�Ȃ��B�J��������W�����W�����~���Ă������ĝ��˂���B�ɓ�����Δi���Ԃ��j�ɂȂ�B
�܂�A�䎷�����̐S�𝛂˂��Ă��邱�Ƃ�Ⴆ��ꂽ�̂ł��B���O�������������āA���ꂪ�Ȃ��Ȃ�����̋ƂɂȂ�Ȃ��͈̂�̂ǂ��ɖ�肪����̂��A����͐M�S�̖�肾�Ƃ������ƂȂ̂ł��B
 �i����Ǐr�搶�̂��b�j
�i����Ǐr�搶�̂��b�j
��y�^�@�̋����Ƃ������̂́A���߉ނ��܂̋������A������F�A�V�e��F���p����āA������͂�����Ǝ����Ă����������B������F�͂��O�����Սs���ƁB���ꂩ��V�e��F�͐M�S�̂��Ƃ���S�ł���ƁA���������Ė��炩�ɂ��Ă����������B
���̋����ɏƂ炵�Đl�ԂƂ������̂��A�l�ԂƂ����܂��Ă����ǎ����ł����A�����Ƃ������̂��@�艺���Ă����B�����ɏƂ炵�Ď������@�艺���Ă������ƂȂ̂ł��B�����������Ƃ͓��a��t�ɂ���ď��߂ďo�Ă����B�����A�V�e��F�ł́A�M�S�����������Ă����l�Ԃ��ǂ��������̂��Ƃ������Ƃ��A�ǂ����܂��n�b�L�����Ă���܂���B
�w���M��x�����Ă��A������F�̂Ƃ���ł͐M�S�����������l�ԁA���O�������������l�ԂƂ����͈̂�̂ǂ������l�ԂȂ̂��A�����������Ƃ��o�Ă���܂���B���낤���āA�V�e��F�̂Ƃ���Ɂu�Q���v�Ƃ������t���o�Ă���܂��B�u�Q����x�����߂Ɂv��S�Ƃ������Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă����������B�������A�V�e��F�̂����t�Ƃ��ẮA���́u�Q���v�Ƃ������t�͂ǂ��ɂ���������Ȃ��̂ł��B����͐e�a���l���u�Q���v�Ɠ��Ă͂߂ċ����̂ł����A���̌��ɂȂ�V�e��F�̂����t���A�����{���Ȃ�u�P�j�q�P���l�v�Ƃ������Ƃ�����B
�u�P�j�q�P���l�v�A�u�j�q�v�Ƃ��u���l�v�Ƃ��A�l�Ԃ������������ʂŌĂԏꍇ�́A����́u�}�v�v�Ƃ������ƂȂ̂ł��B�}�v��������͂�ʂƂ������Ƃ͂Ȃ��Ȃ�B�}�v�ł���ȏ�́A���̐��ʂƂ������Ƃ��ǂ��܂ł�����Ȃ��B�������@�ɂ���������}�v�Ƃ����Ӗ��Łu�P�v�Ƃ����������̂ł��B�u�P�j�q�P���l�v�Ƃ����Ă��S�����������l�Ƃ����Ӗ��ł͂���܂���B�����̈����̂����܂�����ˁB����ǂ��A���@�ɂ��������邩��u�P�v�Ƃ����̂ł��B�S�����������Ƃ��A�s�������\���Ƃ��A�����������Ƃł͂Ȃ��B������ɂ��Ă��A�V�e��F�̒��ڂ̂����t�ł����Ȃ�u�P�j�q�P���l�v�B
�Ƃ��낪�A���A���a��t�̂Ƃ���ւ܂���܂��ƁA�}�v�͖}�v�Ȃ̂�����ǂ��u�f���̖}�v�v�Əo�Ă��܂��B�u�ϔY������Ă���v�Ƃ����Ӗ��ł��B�ϔY������ϔY�ɔ����A�ϔY�ɐU���Ă��̐����̐��E���Ă���A���]���Ă���B���������}�v���Ƃ������Ƃ��n�b�L���o�Ă��܂��B�����̖}�v�A�ϔY������A�Ƃ�����āA�����ċꂵ��ł���A���������}�v�Ȃ̂ł��B�����A�}�v�Ƃ����̂ł͂Ȃ��B
���̓��^�T�t�̂Ƃ���ւ��܂��Ɓu�ꐶ�����v�ƌ�����B�ꐶ�낭�Ȃ��Ƃ����Ȃ��l�ԁA���ꂪ�{��̂��ړ��ĂɂȂ�l�Ԃł��B���ꂩ��A�P�����܂̂Ƃ���ւ���ƁA�u��U�v�Ɓu�t���v�ȂǂƂ������t���o�Ă���B�u��U�v�̕��́A����͂�����ƐS�����悤�Ǝv���Ă��邯��ǂ��A�S�������Ԃɍ���Ȃ��A���������҂̂��Ƃł��B�u�t���v�Ƃ����̂́A����͂����A�Ƃ�ł��Ȃ��߂��Ă���҂ł��B���M�m�s�̂Ƃ���ւ���Ɓu�ɏd���l�v���炢���ƂɂȂ��Ă���B����n�b�L�����Ă���̂ł��B���ꂩ��u�P���̖}�v�l�v�A����͖@�R���l�̂Ƃ���ł��B
���������ӂ��ɁA���a��t�̂Ƃ��납���́A���O�������������l�ԂƂ������̂��ǂ��������̂��Ƃ������Ƃ����Ƀn�b�L���Ǝ�����Ă���̂ł��B
 �i����Ǐr�搶�̂��b�j
�i����Ǐr�搶�̂��b�j
�u�f���̖}�v�v�Ƃ������Ƃ��Ȃ���A���̎��́u���������ρv�Ƃ������Ƃ������Ă܂���܂���B�u�f���̖}�v������ǂ��A���̖}�v�ɐM�S���N����c�v�Ƃ������Ƃł��B�u�N�����v�̂ł͂Ȃ��A�u�N����v�B���������ɑ厖�ł��B�u������v�Ə����Ă���܂�����ǂ��A�u�N����v�Ƃ����Ӗ��ł��B�Ƃ����̂́A�f���̖}�v�ȂǂƂ����悤�Ȃ��̂́A�M�S���N�������Ƃ̂ł��Ȃ��l�ԂȂ̂ł��B�M�S�Ȃ���N�������Ƃ̂ł��Ȃ��l�ԁB������A�N����Ƃ����B
����͌��Ǒ��͂ł��B
���̗͂ɂ���āA�f���̖}�v�̏�ɁA�N�����Ă݂悤���Ȃ��M�S���N�����Ă���B�ϔY�ɐU���ċƂ�A�Ƃɂ���Ă܂��ꂵ��ł���A���������l�Ԃ��A������@���̑��͂������āA�����ɐM�S���N����B�M�S���N����Ȃ�ΐ��������ςł���B
���������ςƂ������Ƃ́A������₷�������Ɓu���̂܂܁v�Ƃ������Ƃł��B�����������Ƃ��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�u���v�Ƃ������́A����͔��ɖʓ|�Ȏ��ŁA�����Ɵ��ςƂ͈���Ƃ����Ӗ��ł��Ȃ��B���ꂩ�琶���͐����A���ς͟��ςƓ���Ƃ����̂ł��Ȃ��B���ɖʓ|�Ȏ��ł��B���́u���v�Ƃ����̂́A��͂ǂ��܂ł���Ȃ̂�����ǂ��A�����͐����A���ς͟��ςƓ�Ȃ̂�����ǂ��A�u��̂܂܂���v���Ƃ������ƂȂ̂ł��B���������Ƃ����̂ł͂Ȃ��B�܂��A�ǂ��܂ł�����Ƃ����̂ł��Ȃ��B��̂܂܂���A�����������Ƃ��u���V�v�Ƃ����B
�����̐��E�ɐ����Ă���̂�����ǂ��A�����ɟ��ς̉e���w���Ă���B��������Ȃ��Ă������Ƃ����A�����������̂�����Ă���̂ł��B�����̂܂ܟ��ςł���B��������߂ğ��ςƂ����̂ł͂Ȃ��B�f���̖}�v�ł�����A�ϔY���N�����A�Ƃ�A����ɂ���ċꂵ��ł����̂ł�����ǂ��A����ǂ��A�u���̂܂܁v�Ƃ����Ƃ���Ɉ��邱�Ƃ��ł���B�����ɂ���Ȃ���u���V�v�ł���B
 �i����Ǐr�搶�̂��b�j
�i����Ǐr�搶�̂��b�j
�w�V�ُ��x�Őe�a���l�́A�u�O���҂͖��V�̈ꓹ�Ȃ�v�Ƌ��Ă��܂��B�����Ɂu���V�v�Ƃ������Ƃ��S�o�Ă��܂��B
�u���̂���ꂢ����ƂȂ�A�M�S�̍s�҂ɂ͓V�_�n�_���h�����A���E�O������V�i���傤���j���邱�ƂȂ��B�߈����ƕ�������邱�Ɣ\�킸�A���P���y�Ԃ��ƂȂ��䂦�Ȃ�B�v
���V�Ƃ������Ƃ́A�F�X�̂��̂����ɂȂ�ʂƂ������Ƃł��B��肪�����Ă����܂�Ȃ��B�����Ă����ɂȂ�Ȃ��B�����������ƂV�Ƃ����̂ł��B
�l�ԂƂ������̂́A�F�X�Ȃ��̂ɖW�����A�����B����ǂ��A���̏��݂͂�Ȏ����̐S�����̂ł��B����������邩�Ƃ����ƁA�����Ƃ������̂�������Ȃ��S���������B������������Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�����̋Ƃ��n�b�L���ƕ�����Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
������A�u���O�������������v�u���O���������������v�Ƃ������Ƃ́A�[�I�ɂ�������A�u�킪�g�̋Ƃ��[���ł����v�Ƃ������Ƃł��傤�B�����A����ȊO�ɂȂ��Ǝv���܂��B���ꂳ������������̂ł��B�䂪�g�̋Ƃ�������A��͉��������K�v���Ȃ��̂ł��B
�Ƃ̕�����Ȃ��l�ԂƂ����̂����������̂ł��āA�F�X�Ə������܂��B�u���̗ǂ������v�́A�Ƃ�������Ȃ�����A����Ȃ��Ƃ������Ă���̂ł��B�Ƃ�������u���̗ǂ������v�͂���܂���B���łƂ��F���Ƃ��A�O�זS�Ƃ��A���炢���Ƃ������Ė����Ă��܂��B�����A���グ������̂ɂ����������A�������ɂ�����߂����đ�����ꐶ�����ɒT���B����Ȃ��̂�����ł͂Ȃ��̂ł��B�s�����������ƌ����Ă���B�u�ǂ�ȓ��ł������v�Ƃ����̂���ԑ���Ȃ̂ł��B�u�Ƃɂ����܂����āv�Ƃ����A���ꂪ��Ԉ��炩�ł��B
�u����ΑP�����Ƃ����������Ƃ��ƕ�ɂ����܂����āA�ЂƂ��ɖ{������̂ށB�v
�t���t�����Ȃ��̂ł��B
������P�W�A�X�N����O�̂��Ƃł����A���邲��k�ւ��Q�肵�܂�����A
�u���@�Ƃ���������ԔN������܂����ȁB����ɂȂ��܂����B�v
�Ɛq�˂��܂����B
�u���������ԔN������āA���N�łS�Q�ɂȂ�܂��B�v
�ƌ����܂�����A
�u�ւ��A�P�O�O�ł����B�v
�u���������ȁA���̊炪�P�O�O�Ɍ����邩�B�v
�u����A�P�O�O���Ⴀ��܂���A��ł��B�v
�ƌ����B
�u���@�Ƃ���A�S�Q�Ƃ�������A�j�̑��ł����B�v
�ƌ����̂ł��B���߂ĕ����Ăт����肵���B
�u����͂ǂ��������Ƃł����B�v
�ƕ�������A
�u�C�����Ȃ����A���̔N���ɂЂǂ��ڂɑ�����������܂���B�v
�ƌ�������A
�u�����������A�Ђǂ��ڂɑ����̂��B����Ȃ���S�����B�ǂ����A�낭�Ȃ��Ƃ����Ă����̂�����A�[���Ƃ�����Ă���̂�����A�Ђǂ��ڂɑ����͓̂�����O�B����͂����A�o������Ă���̂��B�v
�Ɠ����܂�����A���̐l���A
�u���݂����Ȑl�ɂ���������A������Ȃ��܂���ȁB�v
�ƌ����Ă������̂ł��B
���ɂ͓��̗ǂ��������A���p�̗ǂ��������Ȃ��̂ł��B���̂Ȃ��̂��낤���B����l�ɂ͂���A���̂Ȃ�̂��낤���B�������厖�ȓ_�ł��B�l�Ԃ͂ˁA�厖�Ȃ��̂��Ȃ��ƁA���傤���Ȃ����̂�����A�K���N�^������B���ɁA�厖�Ȃ��̂�����Εs�v�Ȃ��̂͂Ȃ��B�����������̂ł��B�K�������Ȃ��Ă���B�v�����̂������Ă���l�͑厖�Ȃ��̂������Ă��Ȃ��B�����āA�v�����̂���������Ă���B�厖�Ȃ��̂������ƁA�����A�v�����̂͂Ȃ��Ȃ�B
���̑厖�Ȃ��͉̂����B�����ł��A���O���ł��B���O���Ƃ����̂́A�䂪�g�̐[���Ƃɂ��Ȃ����Ă���Ƃ������Ƃł��B���O���������������Ƃ������Ƃ́A�����������Ƃł��B�ǂ����Ƃ�����A�������Ƃ��N����܂���B�ƂŐ����Ă���̂ł�����B
���͎v���̂ł�����ǂ��A�������Ƃ������Ƃ����ɂ��肪�����B���������Ă��邩�炵�āA���X�ƐF�X�̂��Ƃɂ����܂��B�����Ő����Ă���̂Ȃ�A�����Ɠ��Ȗڂɂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ǂ��A����ȓ��Ȗڂɂ͗]�肠���܂���B�u����������������ɁA����Ȗڂɑ���Ȃ���Ȃ��v�ƌ����ċ����Ă������l�������B����Ȃ�A�����Ƃ����ł͂Ȃ��B���������l�����܂��B����͉����Ƃ����ƁA��͂�ƂŐ����Ă����邩��ł��B
�Ⴂ�l�ɂ͂܂��Ƃ�������Ȃ��B�ǂꂾ���Ƃ�����Ă��邩������܂���B�U�O����A�i�X�������Ă��܂��B�䂪�g�Ƃ������̂��ǂꂾ���A�����ɋƂ��[���z���Ƃ������Ƃ��i�X�������Ă���B����͂��肪�������Ƃł��B�������m�炳���B����ŁA�@�@���l�́u�������͖@�̕�v�ƌ�����B���@���܂��܂��[������������̂ł��B�ƂŐ����Ă���̂�����A�܂��܂��[���Ƃ�����o�Ă��܂��B�u�����A����ȋƂ������Ă������̂��v�Ƃ������Ƃ��A�����玟�Əo�Ă��܂�����A��������ƁA�Ƃ̐[���������Ƃ������Ƃ��m�炳��邱�Ƃɂ���āA���悢�您�O�������炩�ɂȂ��Ă���B
��X�́A���ł��Ђǂ��ڂɂ����ƁA�u����̂������v�u����̂������v�ƌ�������ǂ��A�����ł͂Ȃ��B�݂�ȁA�������������킪�����ɕԂ��Ă��Ă���̂ł��B���ꂳ���n�b�L��������A�����������Ƃ͂Ȃ��͂��ł��B���ꂪ���O���̐����A���V�̈ꓹ�Ȃ̂ł��B
�����̂܂܁A�����ɁA���̂܂܂ƌ�����A���ꂪ���������ςł��B�u���ρv�Ƃ������Ƃ́u��Áv�Ƃ������Ƃł�����A
�u�����ł��Ȃ��A�����ł��Ȃ��B�v
�Ƃ����S�����܂�̂ł��B�F�X�̖ڂɑ����̂ł��B�F�X�̖ڂɂ͑�������ǂ��A
�u�Ȃ�ł���Ȗڂɑ���Ȃ���Ȃ��̂��B�v
�u���̈��ʂŁA����Ȗڂɑ���˂Ȃ��̂��B�����B��Ȃ��B�v
�Ƃ������Ƃ��Ȃ��̂ł��B�[���[���Ƃ�����Ă��܂�����A���̋Ƃɉ����ĐF�X�Ȃ��Ƃ͋N�����Ă��邯��ǂ��A����Ɉ�����������Ƃ������Ƃ��Ȃ��B�ߎS��������Ƃ������Ƃ��Ȃ��B�ǂ����Ƃ����������Ƃ��ƕ�ɂ����܂����Đ����Ă�����B���ꂪ�A
�u�������Ȃ킿���ςȂ�Əؒm�����ށv
�Ƃ������Ƃł��B�u�v�Ƃ���܂�����A����͈�̌��ł��B���M�S�ɂ͂����������̈Ӗ�������B���̂܂܂Ƃ����A��̑傫�Ȍ��ł��B���̂܂܉����������Ƃ͂Ȃ������A����������̕��̒q�d�ł��B���̒q�d�����O���������������l�Ԃ����Ă���B���Ɉ��炩�ɁA�������A���邭�����̒�������Ă�����B���������̂����V�̈ꓹ�ł��B
 �i����Ǐr�搶�̂��b�j
�i����Ǐr�搶�̂��b�j
�����y�͈���ɕ��̐��E�ł��B����ɕ��̐��E�ʌ����y�ł���ƌ������Ƃ�����̂ł�����ǂ��A���������ʌ����y�Ƃ������ƂɂȂ�ƁA����͐F�X�ȕ����܂������܂�����A�����鏔���̐��E���u���ʌ����y�v�ƁA���o�̒��ł͂��������Ă���B�����́u���v���u���ʁv�ƌ��������Ă���̂ł��B�e�a���l�́A�n�b�L���u�y�͂܂����ꖳ�ʌ����y�Ȃ�v�Ɓw���s�ؕ��ށx�^���y���̒��ɋ��Ă����܂��̂ŁA����ɕ��̐��E�����ʌ����y�A���ʂ̌��̐��E���Ƃ������Ƃł��B����ł����̂ł�����ǂ��A���̌��̈Ӗ��͏����̐��E�Ȃ̂ł��B�����͐�����Ȃ������܂�����A�����̌����̐��E�����ʂɂ���Ƃ����Ӗ��ŁA���ʌ����y�B���������ӂ��Ɏg���Ă���̂����o�ł��B
���̖��ʌ����y�Ƃ����A�����鏔�����̌����鐢�E�Ƃ������̂́A����́A����ɂ��܂̌��ɂ���ċP���Ă���̂ł�����A���������āA�����̐��E�ł���܂܂��A���͈���ɕ��̐��E�ł���ƁA���������ӂ��ɐe�a���l�͎���āA����ɕ��̍��̂��Ƃʌ����y�Ƃ����Ă���̂ł��B
 �i����Ǐr�搶�̂��b�j
�i����Ǐr�搶�̂��b�j
�u���v�Ƃ������ς̐��E�֊��S�ɓ��B����Ƃ��ӂ��Ɏ��Ȃ�A����͐����Ƃ������Ƃł��B�����Ȃ�A��͂菃���Ȗ����Ƃ������A�Ƃ����悤�Ȍ`�ōl�����܂��B������A����������ƐϋɓI�ɍl����ƁA�����A��y�ƒ������Ă���Ƃ����悤�ȈӖ��������ɍl������̂ł��B�M��Ȃ�A�����ɏ�y�ƒ�������B�s�������Ă��܂��Ƃ����̂ł͂Ȃ��B��y�ƒ��ڂɌ��т��A�����������Ƃ��\�����Ă���̂ł��B�����ɂ��Ă͖�����ǂ��A�M�����������Ȃ�A�����Ƃ����ɏ�y�����т��Ă���A��y�ƂȂ���B���������Ӗ��Łu�K���v�Ƃ������t������̂ł��B
��������킯�ł��B���ԓI�ɂ͖B�̏ꍇ�͐����ł��B���ꂪ�����Ƃ������ƂɂȂ�Ɖ����B���������B
�����Ƃ������t���A��y�Ƃ̒�����\�킵�����t�ł��B��y�ƒ��ڂɌ��т��A��y�ƒ������邩��A�����ɏ�y�̌����^�����A�܂���y�̌����Ƃ������̂��^�����Ă���B�����Ƃ����`�ŏ�y����������A��y�̌����^�����A��y�̌������̂��̂��l�Ԃ̏�ɗ^�����Ă���B�ԈႢ�Ȃ��ɕ��ɂȂ�Ƃ������Ƃ��A��\���ɂ́A�u�����ڂɏZ���A�K���œx�Ɏ���v�Ƃ����Ă���B�����ł́u�K�����ʌ����y�v�Ƃ�����B�œx���P�Ȃ�œx�łȂ��ɁA�P�Ȃ韸�ς̐��E�łȂ��ɁA�u�M�S�ɂ���ĊJ���鐢�E�́A�{��̏�y�Ȃ̂��v�Ƃ������Ƃł��B
����͉����Ƃ����ƁA�M�S��^���悤�Ƃ����Ƃ���ɔ@���̖{�肪����̂ł��B���������āA���̔@���̖{��ɉ����{�����ꂽ�̂��A���ꂪ�M�S�ł��B�����ɖ{��̏�y���J����B���������Ӗ��ŁA�����œx�Ƃ��킸�Ɂu�K�����ʌ����y�v�Ƃ����Ă���B��\���̂Ƃ���ł͖œx�Ƃ����Ă��邯��ǂ��A�����ł͐M�S�ɂ���ĊJ�����̂��Ƃ������Ƃ��n�b�L�������邽�߂ɁA���Ƃ���Ɂu���ʌ����y�v�ƕ\�킳�ꂽ�̂ł��B�{��ɂ��Ȃ����Ƃ������Ƃ́A���ǁA������������Ƃ������ƂȂ̂ł��B���̂��Ƃł͂���܂���B������������Ƃ������Ƃł��B���ꂪ�M�S�Ȃ̂ł��B
��X�́A���@�Ƃ����ƁA�����܂�������Ƃ����悤�Ȋ��Ⴂ���悭����̂ł�����ǂ��A�����Ă���悤�Ȑl�Ԃ̕����镧���܂Ȃ�A�{���̕����܂ł͂Ȃ��ł��傤�B�Ԉ�����S���������悤�Ȃ��̂́A���ׂĊԈႢ�ł��B
���q�����̊J�c�����ׂĔ�b�R�֓o���āA���Ƃ����ĕ����܂��낤�Ƃ��č���חコ�ꂽ�̂ł�����ǂ��A�ǂ̕��������炸���܂��ŁA�Ƃ��Ƃ��R������Ă���ꂽ�B����Ŕ�b�R�̋������Ԃɍ���Ȃ����Ƃ��݂�ȕ��������̂ł��傤�B
�e�a���l�̏ꍇ�́A�R��������Ė@�R���l�̂Ƃ���֍s���ꂽ�킯�ł��B�����āA���������������Ƃ����ƁA�����܂����������̂ł͂Ȃ��A�����܂̐S�����������B�{�肪���������B�����܂͕�����Ȃ��Ă��A�����܂̐S�͕�����̂ł��B�����܂͂����炩��s�������ē͂��Ȃ��̂ł��B����ǂ��A���肪�������Ƃɂ͌��������炱�����֗��Ă���A�������Ă���B�{��́A��X�̂Ƃ���֗��Ă��܂��B���̐S�͉�X�ɒ�����Ă���B������A��X�͂���ɂ��Ȃ������Ƃ��ł���̂ł��B
�����܂͎������Ɂu�����g��m��v�u�����ɖڂ��o�܂��v�ƁA��������Ă�����B���ꂪ�{��ł��傤�B��P�W�Ԗڂ̊�ł��B�u�����g�ɖڊo�߂�v�Ƃ����̂����̐S�ł��B���̐S�������������Ƃ������Ƃ́A�䂪�g�ɖڂ��o�߂��Ƃ������Ƃł��傤�B�����Ė{��̐S�������������Ƃ����Ƃ���ɖ{��̏�y���J���Ă���B
���������Ӗ��ŁA���o�̖{��̂Ƃ���ł́u�K���œx�v�Ƃ���܂�������ǂ��A�P�Ȃ�œx�ł͂Ȃ��B�{��̏�y�Ȃ̂��Ƃ������Ƃ��n�b�L�������邽�߂Ɂu���ʌ����y�v�ƌ��������Ă���̂ł��B
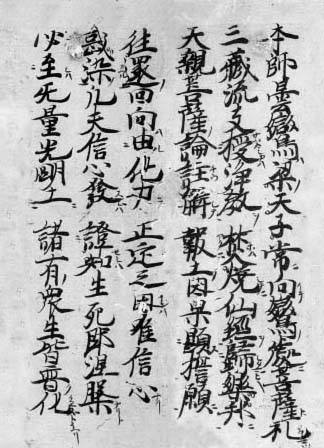 ���a��t�́A�V�e��F�́w��y�_�x�ɒ��߂��{���āw�����_���x���Q�����A����ɔ@���̏�y�́A���̏o���オ��@���ʂ��A�݂Ȏ����@���̐���ɂ���Ăł������������Ƃ������A����ɁA����͑S���O�����~�ς��邽�߂ł���Ɛ����ꂽ�̂ł���܂��B
���a��t�́A�V�e��F�́w��y�_�x�ɒ��߂��{���āw�����_���x���Q�����A����ɔ@���̏�y�́A���̏o���オ��@���ʂ��A�݂Ȏ����@���̐���ɂ���Ăł������������Ƃ������A����ɁA����͑S���O�����~�ς��邽�߂ł���Ɛ����ꂽ�̂ł���܂��B